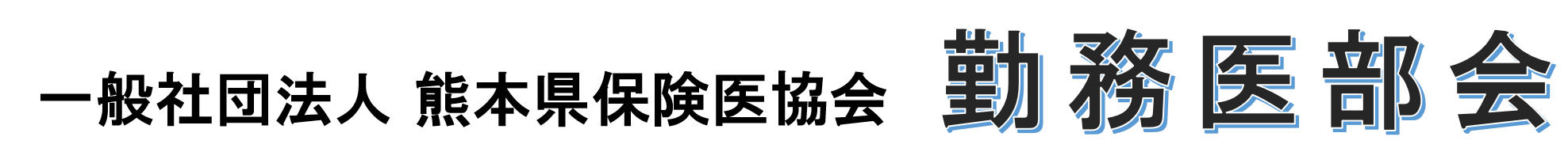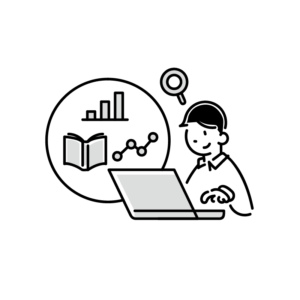気管支喘息の治療の変遷
気管支喘息は成人の5%前後、小児の10%前後の罹患率を示すありふれた疾患だが、その病因と治療に関してはこの50年間で大きな進歩があった。1970年代までは1型アレルギーが病因とされてきたが、成人喘息を中心にIgEに依存しないタイプの喘息が認識されるようになり、好酸球性気道炎症がその病態で重要なことが判明してきた。
1990年以降は気管支拡張剤や抗アレルギー剤を中心とした薬物治療から、吸入ステロイド(ICS)の連用で気道炎症を抑える治療へと進化した。ICSの連用によって日本の喘息の死亡者数は1990年代初期の6〜7千人から2020年には千人台まで減少した。
しかしICSは効果発現まで数日はかかっていたため、単独でアドヒアランスが悪いことが問題であった。2000年代半ばにICSと長時間作動型βアゴニスト(LABA)の配合剤が臨床に導入されてから、患者が治療効果を吸入初日に実感することでアドヒアランスが大きく改善した。
2020年代になってLAMA(長時間作動型抗コリン薬)が吸入配合薬に導入され、トリプル治療としてICS+LABA で効果不十分な症例に有効である事が示された。COPD合併例もトリプル治療のよい適応である。
ICS+LABAそしてLAMAが気管支喘息の維持療法とされるが、急性発作の時にはSABA(短時間作動型βアゴニストの使用が基本であり、以前から発作時によく使用されていたキサンチン薬(ネオフィリン)の経静脈投与は避けられるようになった。その理由はテオフィリンの副作用(頻脈、嘔気、時に痙攣など)がコントロール困難な事にある。なお急性発作にSABAだけで症状が軽快しても気道のアレルギー性炎症が持続するので、救急外来ではステロイド薬の全身投与(経口もしくは経静脈投与)が必要である。
従来から使用されていた抗アレルギー薬は気管支喘息ではパワー不足なので、アレルギー性鼻炎合併例以外では一般臨床では使用頻度が減ってきている。唯一ロイコトリエン受容体拮抗薬は夜間早朝の喘息症状の緩和に有用である。なお、気管支拡張剤の経口投与は頻脈、振戦などがあるためにほとんど使用されなくなった。LABAの貼付薬は吸入がうまく出来ない症例ではよく使われている。
以上のICSのトリプル治療やロイコトリエン受容体拮抗薬などでもコントロールが困難な重症型に対しては抗体製剤(抗IgE、抗IL-6 など)の注射剤が使用可能であり、一定の有効性がみられているが、高価格がネックとなって広く臨床の場で使われるまでには至っていない。
一般内科医ならびに全身管理が必要とされる外科系医師には吸入薬の使用法について習熟する必要がある。なぜならば吸入療法は患者がその必要性を理解して、吸入手技をマスターしない限り、その役割が果たせないからである。薬剤師や看護師などのコメディカルに患者教育を協力してもらうことが喘息コントロールのキーポイントであること強調したい。
桜十字病院内科 吉永 健
![]()